クーポン獲得
- STEP1. 内容入力
- STEP2. 内容確認
- STEP3. 完了
入力が必要な項目は、
残り件です。
結婚のお祝いや出産のお祝い等の慶事(けいじ)ごとでも、お見舞いやご香典等の弔事(ちょうじ)ごとでも、どちらの場合でものし袋にお金を包んでお渡しすると思います。
それぞれ、慶事ごとは祝儀袋、弔事ごとは不祝儀袋とご理解されていらっしゃると思います。
今回は、その「のし袋(祝儀袋・不祝儀袋)」についての豆知識をご紹介します。

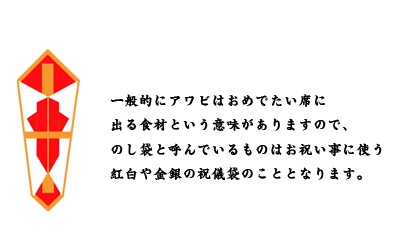
のしとは、祝儀袋や熨斗紙などの右上にある飾りのことを指します。
その語源は、「のしあわび」にあります。「あわびをのす」つまり、鮑を薄く長くはぎ、引き延ばして乾かす事を意味します。
昔より鮑は貴重な食材で神事のお供え物として用いられました。
乾燥した鮑は栄養価が高く、保存食として、不老長寿の印と重宝がられ、贈答品の代表的なものでした。
鮑以外のものが贈答品に用いられるようになっても、鮑は添えられ、それが現在の小さなのしに変化したと考えられます。
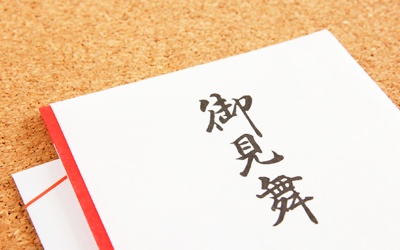
一般的に結婚祝い等の慶事ごとにしか”のし”は使いません。香典返しなどの弔事の場合には、「生臭物(なまぐさもの)を忌み嫌う」という理由から、病気見舞いや災害見舞いの場合には、のしあわびには「引き延ばす」という意味があることから”のし”はつきません。
また”のし”がつかない不祝儀袋につきましては、本当は、のし袋とは呼びません。本来は、祝儀袋とあわせて「金封」と呼びます。

水引は、神様にお供えをする際にかける「しめ縄」が変形したものといわれています。
和紙をこよりにして、水のりを引いて乾かして作ったことから「水のりを引く」略して「水引」と呼ばれるようになりました。
昔、宮廷への献上物を紅白の麻のひもで結ぶ風習があり、室町時代に麻のひもが現在の和紙の水引に変わっていったようです。
ただ一概に水引といっても「本数、色、結び方」用途に適したルールが存在します。