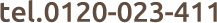-
水引のルールについて
「内祝」や「御祝」等の表書きに関しましては、絶対というルールは存在しません。例えば、「いつもありがとう」や「お母さんありがとう」等の表書きでも通用します。
でも水引に関しては、絶対というルールが存在します。今日は、水引の絶対的ルールについてご説明いたします。 
水引の絶対的ルールって何?
-
1水引の色について
水引の色は、鎌倉から室町時代までは白一色でした。そのうちに染めたものが使われるようになり、紅白、金銀、黒白、黄白、青白などの染め分けが誕生しました。その後には、双金、双銀の一色のものも使われるようになりました。
現在では、一般の贈答や慶事には紅白の水引を用い、その中でも特におめでたいとされる結婚にまつわる贈答や高価なものを贈る際には、金銀の水引も使用されます。
これに対して、弔事では黒白や黄白の水引が使用されます。 -
2水引の本数について
水引の本数は、3本、5本、7本と奇数のこよりを束にして使用します。
基本の本数は5本で、3本は5本を簡素化したもの、7本は5本を丁寧にしたものとなります。
一般的には、「出産内祝」等の慶事ごとには、7本の水引を用いる事が多く、「快気祝」等のお見舞いや「香典返し」等の弔事ごとには、5本の水引を用います。
慶事の中でも特におめでたいとされる結婚にまつわるものには、5本の水引を2束にした10本の水引が用いられます(両家並びに男女がひとつになる事を表しています。)10本の水引が用いられるのは、結婚にまつわる事柄だけです。 -
3水引の結び方について
現在の水引の結び方は、”ま結び” ”もろなわ結び” の2種類が変化したものだといわれております。一般的に「結び切り」と呼ばれる結び方は、本来、”ま結び”と呼ばれるものです。また、「花結び」「蝶結び」と呼ばれる結び方は、本来、”もろなわ結び”と呼ばれるものです。
結婚にまつわるものは、すべて「結び切り」となりますが、これには「人生の中で一度限り」という意味合いから用います。弔事ごとに関しては、「不幸が再び起きないように」という願いから「結び切り」を用います。
慶事ごとに関しては、片方の水引を引くとほどけ、再度結ぶことができることから、「何度でも繰り返してよい」という意味合いで「花結び」「蝶結び」が用いられます。
ギフトエイドの熨斗サービスはこちら
表書きが同じ場合でも水引の違いで何のお返しかわかるって本当なの?
-

本当です。表書きに関しましては、ある程度のルールはありますが、比較的自由な言葉を使用することが出来ますが、水引に関しては、絶対的なルールが存在します。
上の写真でご説明しますと表書きはすべて内祝ですが、異なる点が
①熨斗あり・水引き:紅白10本の結び切り
②熨斗あり・水引き:紅白7本の蝶結び
③熨斗あり・水引き:紅白5本の結びきり となります。
この違いから、①は「結婚内祝い」②は「出産内祝い等の慶事の内祝い」③は、「快気祝い」であることが分かります。
見分け方は、A:水引の結び方(蝶結びか結び切りか)B:水引の本数 C:熨斗(のしアワビ)の有無 で判別します。
まず、Aの水引の結び方についてですが、蝶結びは、「何度繰り返しても良い」と思われるものに使用されますので、出産内祝い・入学内祝い・新築内祝い等の慶事ごとの内祝いである事が分かります。
もう一方の結び切りは、「人生の中で一度限り」と思われるものに使用されますので、病気・災害のお見舞いのお返し等での内祝いであることが分かります。
次にBの水引の本数ですが、基本的に使用される数が「5・7・10」となります。
5本は、病気や災害のお見舞いのお返しの内祝いの際に使用します。
7本は、慶事ごとでの内祝いの際に使用します。
10本は、結婚にまつわる内祝いの際に使用します。
Cの熨斗(のしアワビ)の有無については、のしアワビがおめでたい慶事ごとに用いることから、のしがある場合は、結婚や出産等の慶事ごとであることが分かります。
逆にのしがない場合は、病気や災害等のお見舞いのお返しの内祝いである事が分かります。
※インターネット上では、病気や災害のお見舞い返しの熨斗紙に「のしアワビ」がついている場合もありますが、本来の意味を考えると、つけない方が良いと考えられます。