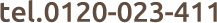-
結婚・出産内祝い|のしの選び方・書き方は?
結婚や出産の際にお祝いをいただいた際は、お返しとして内祝いを贈るのが一般的です。しかし、内祝いとして何を贈ればいいのか、のしはつけるべきなのかわからない方もいるでしょう。とくに職場の上司など目上の方に内祝いを贈るときは、失礼にならないようマナーを押さえておきたいものです。
この記事では、のしの由来や水引の種類、のしの掛け方のほか、内祝いの金額の目安や内祝いを贈る時期について解説します。ぜひ参考にしてください 
のしとは?
現在用いられている「のし」は、かつて「のしあわび」を添えて贈りものをした習慣に由来しています。のしあわびとは、干したアワビを薄く伸ばしたもので、あわびが長寿や繁栄の象徴とされたことから縁起物とされました。
のしあわびの習慣は次第に簡略化され、紙を折って作った「熨斗飾り」が広く用いられるようになりました。さらに現代ではとくに形式張らない贈りものの場合には、水引や熨斗飾りが印刷された「のし紙」が用いられます。
ただし、鮮魚や肉などの生ものを贈りものとする場合や、病気や災害へのお見舞いをする場合、弔事のときには「のし」のない、水引のみが印刷された掛け紙を使用することがマナーとされています。注意してください。
水引の種類
水引にはいくつか種類があります。ここでは、その種類とそれぞれが用いられるシーンについて解説します
蝶結び(花結び)
蝶結びは花結びとも呼ばれる水引の一種です。蝶結びは結んで解くという行為を何度でも繰り返せることから、何度起こっても喜ばしい出来事を祝うときに用います。出産や開店、入学や進学、新築や長寿、お中元や年賀などの慶事一般にともなう贈りものをする際には蝶結びの水引を用います。結び切り
結び切りは結んでしまうと端を引っ張ってもほどけないことから、弔辞や繰り返しが望まれない一部の慶事の際の贈りものに用いられます。たとえば結婚祝いの際には「繰り返すことがないように」という意味で結びきりを使うことがマナーです。同様の趣旨で退院祝いや快気祝いにも結び切りが用いられます。

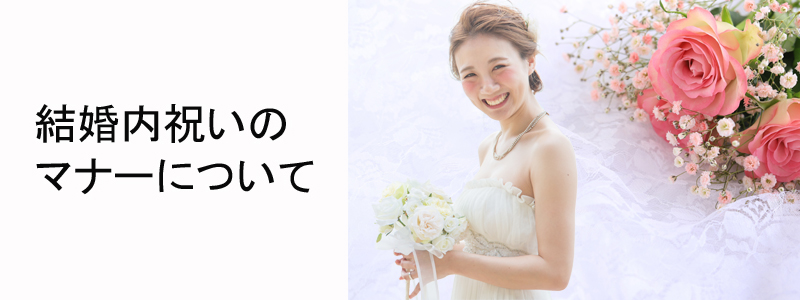
結婚内祝いののしのマナー
ここでは、結婚祝いにつけるのしのマナーについて詳しく解説します。
水引は「結び切り」を選ぶ
結婚内祝いの贈りものには、水引の色が「紅白」や「金銀」で、本数は10本、結び方は「結び切り」になっているものを選ぶのが一般的です。一般の慶事では蝶結びを選びますが、結婚を何度もすることは死別や離婚が前提となってしまうため、結婚の内祝いには「一生結ばれ続ける」という願いを込めて結び切りを用います。
上段は「寿」「内祝」「結婚祝」のいずれか
のし紙の上段に書くのは、贈りものの目的です。結婚内祝いの場合、水引の上段に「寿」や「内祝」、あるいは「結婚内祝」と記します。結婚式当日に贈る場合には「寿」とする場合が多く、後日贈る場合は「内祝」とされるケースが多いです。現代ではあらかじめ印刷されている紙もあるため用途に合わせて使い分けましょう。
下段は「夫婦の新姓」または「二人の名前」
水引の下は贈り主の名前を記載する部分です。結婚内祝いは夫婦からの贈りものであるため、夫婦の新しい苗字を記すか、夫婦の名前だけをあるいは夫の姓名と妻の名を並べて記入するのが一般的ですが、両家の家名を記す場合もあります。さらに記入の仕方を、以下で解説します。
連名の場合の書き方
新郎新婦の名前を連名で記す方法はいくつかあります。一つは新郎新婦の姓を記さず、名前だけを並べて記入する方法です。二つめは新郎の苗字と名前を記し、その左に新婦の名前だけを書く方法です。
三つめは夫婦の新しい姓をのし紙下段の中央に書き、その下に夫婦の名前を並べて書く方法で、見た目にバランスがいいところが特徴です。また、両家の姓だけを書き、新郎新婦の名前を書かない方法もあります。
毛筆・筆ペンなどで書く
のし紙の表書きをする際には毛筆や筆ペン、あるいはサインペンなどを用います。いずれの場合も、濃い墨で太く、ハッキリと楷書で書くことがポイントです。ボールペンや万年筆はたとえ濃いインクであったとしても避けてください。もちろん鉛筆で書くこともマナー違反になります。
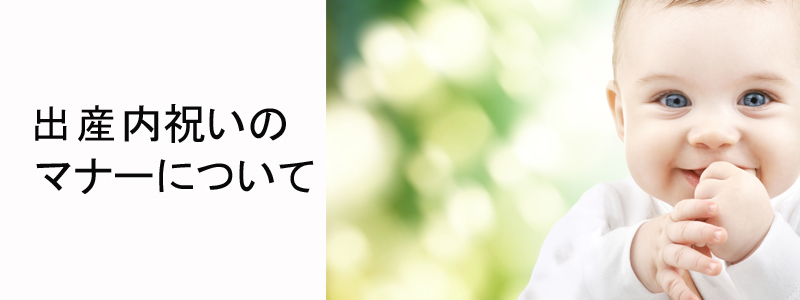
出産内祝いののしのマナー
ここでは出産内祝いの、のしのマナーについて解説します。
水引は「蝶結び」が一般的
出産は何度繰り返してもおめでたい慶事ですので、何度でも結んで解ける蝶結びになっている水引を選びます。水引の色は「紅白」を選び、本数は5本のものが一般的とされていますが、少しあらたまった贈りものをする際には7本のものを使う場合もあります。
上段は「内祝」または「出産内祝」
出産内祝いの、のし紙にも表書きが必要です。水引の上段には「内祝」や「出産内祝」と記します。あらかじめ上段が印刷された状態で販売されている、のし紙を使用してもマナー違反ではありません。
下段は赤ちゃんの名前を書く
出産内祝の贈りものは、赤ちゃんの名前を知ってもらうためにも赤ちゃんの名前で贈ります。水引の下段には赤ちゃんの名前のみを書くのが一般的ですが、名前の前に「命名」と入れたり、赤ちゃんの姓名を記したりしても差し支えありません。誤読や先方が読み方に迷ってしまうことを避けるために、読み方がかんたんな名前であってもふりがなを振っておきましょう。

「内のし」と「外のし」どちらにするべき?
のし紙をつける方法には、「外のし」と「内のし」の2種類があります。ここではそれぞれの違いと、どういった使い分けがされるかを解説します。
「内のし」「外のし」とは?
内のしとは、品物にのし紙をつけた上から包装紙をかける方法です。のし紙が包装紙の内側になるため、贈りものの外側からはのし紙が見えません。贈りものをするにしても控えめな印象や奥ゆかしさをもたせたい場合に用いられる方法です。
逆に、外のしでは品物を包装した外側にのし紙をかけます。のし紙が露出しているため、誰がどういった名目で贈ったものであるかが一目瞭然になります。一度に大量の贈りものが届くような時期や、交友関係の広い贈り先である場合には外のしにしたほうがいい場合もあります。
内祝いは「内のし」がおすすめ
内祝いは「祝いごとのお裾分け」である以上、控えめにすることが望ましいとされます。一般的に贈りものでは「外のし」とされることが多いですが、内祝に限っては「内のし」が用いられることが多いです。手渡しの場合は外のしとする場合もありますが、宅配業者による配送を依頼する場合、内のしにすることで輸送中にのし紙が破れてしまうことを避けられます。

結婚・出産祝いをいただいたらすること
ここでは、結婚祝いや出産祝いをいただいたらどういったことを、どういった順番でおこなうべきであるか解説します。
手紙または電話ですぐにお礼を伝える
なにかお祝いをいただいたら、できるだけ早くお礼をするようにしましょう。とくに目上の方からお祝いをいただいた場合、手紙でお礼をしたためるとより丁寧な印象をもってもらえるでしょう。電話でお礼をいう場合は、基本的には日中に電話をするようにします。夜にかけるとしても、21時を過ぎないようにしましょう。
1~2か月以内に内祝いを贈る
内祝いは、お祝いをいただいてから1~2ヶ月以内に先方の手元に届くようにします。手配から実際に届けられるまでいくらか時間がかかることも考慮して、とり急ぎお礼を申し上げたあとは、1ヶ月以内に贈りものの手配を始めましょう。
内祝いの金額目安は?
内祝いは、いただいた贈りものの3分の1から2分の1程度を目安とします。ただし、贈る側と受け取る側で相場の感覚にずれがある可能性があります。たとえば、先方が2分の1相当を期待していたところに、3分の1相当の品物を贈ってしまうと信頼関係が壊れてしまう恐れがあります。
のしがないお祝いをいただいた場合はどうする?
職場の同僚や友人などからもらったお祝いに、のしがついていないこともあるでしょう。しかし、いただいたものに、のしがなかったとしても内祝いを贈らなくていいわけではありません。のしのない贈りものをいただいたとしても、内祝いにはのしをつけて贈ることがマナーです。
まとめ
贈りものへのお返しとして内祝いを贈る際には、のし紙の選定や内祝いの金額の目安などのマナーがあります。マナーをしっかり押さえて内祝いを贈れば、職場の上司や目上の親戚などにも一目置かれることでしょう。
内祝いの贈りものに何を選ぶか迷っている方には、ギフトエイドをおすすめします。おしゃれで品質の内祝いの品を多数掲載しています。
商品代金が3,000円を超えると送料が無料になるため(沖縄・北海道を除く)、限られた予算内でのプレゼント選びも可能です。ぜひご利用ください。